結果は0対0の引き分け。FC今治(以下今治)は後半9分に退場者を出してしまうが、残りの時間を粘り強く守り、藤枝MYFC(以下藤枝)に得点を許さなかった。一方の藤枝はこれで開幕戦に続いての無得点試合となってしまった。しかも、数的有利の試合でスコアレスドロー。得点力不足が非常に懸念される状況である。
以下、この試合で藤枝に対して感じたことを書いてみたい。
●攻撃の全体的なリズムが単調で緩急がない。
●攻撃時の選手間の距離が一定で変化に乏しい。
●2シャドーと2ボランチがそのまま縦関係のポジショニングで守るため、中盤の両サイドにスペースができやすい。そのため、容易にサイドへボールを回されて、そこを攻撃の起点にされやすい。
●シュートが枠に飛ばない。
〇右ウイングバックの川上選手のロングランニングがいい。走り出しのタイミングが良いので絶好のスルーパスを呼び込んで大きなチャンスを演出した。
パスワークやドリブルで相手をはがそうとしているのはわかるが、その動きのリズムが単調だと感じた。基本的にはトップスピードでの動きが多い。しかし、今治の選手はその動きに同調して対応していた。なので、体を当てられたりボールを突っつかれたりしてしまう。例えば「緩」で相手を引き寄せ、「急」ではがす。そのように、相手に後手を取らせながらゴールへ迫る。そういう崩しが欲しい。高い攻撃強度を出そうとはしているが、相手に同調されている状態でパスを出したり、シュートを打ったりしている。だから結果を出せるような攻撃に結びついていないのだと思う。
攻撃の時は、今治の陣地に藤枝の多くの選手がポジショニングすることになる。その時に、選手と選手の距離が等間隔で、ピッチ上に選手がバランス良く散らばっているように見える。その陣形にこだわって攻撃しているように感じた。確かにその方がピッチを有効に使える。ボールもある程度正確につなげて、ある程度の距離を効率良く動かせる。そのうえ、ポジショニング感覚も掴みやすく、自分の役割もはっきりすると思う。しかし、相手も同様に守備のポジショニング感覚を掴みやすく、自分の役割がわかりやすいだろう。特に肝心のアタッキングサードにおいて、等間隔の距離感をベースにした教科書的な攻撃は、守る側からするとマークにつきやすい感覚を覚えるのではないか。時間が経つほどに、藤枝の選手の配置イメージが今治の選手の中に確立してきたのではないだろうか。藤枝はボールを効率的に動かして、最後はフィニッシャーにボールを届ける意図があるのだろう。2024年のシーズンでは、主に矢村選手がフィニッシャーの仕事をしてくれて得点が取れていた。しかし、今シーズンのここまでは上手くいっていない。もっと、選手間の距離を変化させながら流動的に攻撃した方がいいと思う。この試合でも後半開始直後の攻撃で、3、4人の選手が密集して短いパスを交換し、左サイドに相手のディフェンダーを集めたところで、すかさず長めのパスを右サイドの川上選手に通した場面があった。川上選手からのクロスは合わなかったが今治の守備を空転させた良い攻撃だった。しかし、その他の多くの時間では、攻撃のリズム、そして選手間の距離に変化が少なく、今治の守備を惑わせていない。見ていても藤枝が得点できる予感は大きくなかった。今の攻撃では相手陣地で、ある程度はボールを握れるかもしれないが、あくまでも守備側の管理下で攻撃しているため得点は生まれにくいと思う。
シュート精度の低さが、この試合でも露呈された。シュートに至るまでの攻撃について感じたことを前述したけれど、その攻撃の過程で感じる閉塞感が藤枝の各シューターに伝播しているように思えて仕方がない。まるで、その閉塞感によって、シュートというエキサイティングなプレーの爆発が阻害されているかのようだ。もっと自由で創造的な藤枝の攻撃が見たいのだ。相手の守備対応の上を行く藤枝独自の魅力ある攻撃を見せて欲しい。その攻撃ができれば、閉塞感から解放された本来のシュートが戻って来ると思う。そして歓喜のゴールは、今の藤枝を覆っている重苦しい空気を消し去ってくれるはずだ。

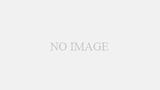

コメント